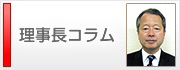- トップページ
- > 理事長コラム

下期以降も続く厳しい経営環境を共に戦い抜きましょう
創業時の感謝の気持ちを忘れないユニクロ
皆さんご存じかと思いますが、ユニクロが5月23日に全国紙に“失われた30年と、失われなかった40年。”をキャッチフレーズにした全面広告を出しました。
確かに私たちは失われた30年と言っていますが、ユニクロにしたら、失われなかった40年なのです。平富郎エコス名誉会長が景気は自分で作るものと言われていますが、ユニクロはまさにそれを実行した好例です。
今から40年前に遡ると、ユニクロは1984年6月2日に広島市袋町の裏通りで1号店をオープンしました。開店時間は早朝6時という奇策。誰も来てくれないのでは?店長でさえそう思うほどでした。ところが大行列、というより大群衆が集まってきた。
「早朝から並んでくださったお客様になにか感謝をお伝えしたい!とお配りしたのが、あんぱんと牛乳でした。あの日の気持ちはユニクロの初心。いまへとつづく感謝祭の原点です。」と広告には書いてあります。
素晴らしいユニクロの成長と軌跡が1枚の広告で謳いあげられている。エコスさんはこれに近いことをやり、ここまでこられていると思いますが、私たちもこれに元気づけられると共に、かくありたいと思うところであります。
ユニクロの40年を顧みると、世界で3,500店、時価総額は12.7兆円、売上は3兆円超。海外事業が国内の1.5倍。アメリカ、ヨーロッパなど地域に合わせて経営判断できる体制を構築して更なる発展に向けてチャレンジしていこうとしています。
我々もこうした企業を模範にしながらやっていかないといけないと感じています。
「世界一」と言い始めた時から衰退始まる
一方で、成功していない企業もあります。
シャープの液晶は日本でしかできない、世界最先端のモノ作りを実現した、「世界の亀山モデル」と自画自賛していました。亀山工場は液晶パネルからテレビまでを一貫生産する、垂直統合型工場と言われていました。要するに部品から完成品まで造り上げた。2002年上期、シャープは米国のシェアで33.5%を占めた。メーカーが「我が社は世界一」と言い始めた時から衰退が始まっていて、2024年9月には大型液晶パネルの生産を終了します。
経営が苦しくなると、液晶パネルを海外メーカーに外販したり、コスト競争に巻き込まれ、2015年には台湾のホンハイの傘下に入り、2018年には黒字転換、2020年には大幅黒字で再建が完了した。22年には夢をもう一度と、堺ディスプレイ・プロダクト(SDP)を買い戻した。しかし2023年にはSDPの業績悪化で減損損失を計上。24年9月に大型液晶パネルの生産を終了することになったのです。
この例から、過去の栄光、成功体験に固執し冷静な状況判断が出来ず、結果として変化に背を向けたと言えます。平名誉会長が良く言われることですが、「成功の原因が失敗を作る」と感じています。
日本もシャープと同じで、失われた30年で国力は衰退。一人当たりのGDPは韓国、台湾に抜かれている。その中で、アニメの評価、インバウンド、外国人労働者で持ちこたえている状況。なんとなく昭和の成功体験の中で、世界の急激な変化に対応出来ないでいる。「日本がスゴイ」、という成功体験から、「日本がヤバイ」と変わっているのが現状。私たちもそれを日々感じながら経営しているのが現実だと思います。
成長著しいシンガポール
先日シンガポールに行ってきましたが、その発展を目の当たりにしてきました。
シンガポールの人口は日本の4%、面積は0.2%、GDPは6.3%。しかし一人当たりGDPは日本の約2倍。サービス産業、製造業を基盤に、情報、金融産業が急成長している。いろいろな意味でアジアのハブとしてトップに立っている。エアポートがハブになり、海運でもハブになっている。政治的にも安定していて、汚職も少なく、公的機関の透明性は高い。
1965年にマレーシアから独立し、中国人のリー・クワンユーが長く政治のリーダーでいて、その息子のリー・シェンロンにその座を譲り、シェンロンが今年の5月に任期を終えた事に伴いローレンス・ウォンが首相になったばかり。
成長の象徴になったマリーナベイ・サンズは2011年に開業している。3棟の屋上を船の形をした構造物で繋いでいる有名なホテルですが、現在までも統合型リゾートホテルとしてどんどん成長してきている。その中のショッピングセンターには世界のブランドが全て集中していて驚かされます。あれだけ集中しているのはおそらくあそこだけ。
シンガポール大学は世界のトップで東京大学よりかなり上に位置づけられています。
シンガポールの地下鉄に乗って驚きましたが、非常に乗り易い。東京の地下鉄の路線図ダイヤグラムが見やすいと他の国々のモデルになったことがあるが、シンガポールのダイヤグラムは非常に見やすい。一つのカードで乗り回れる。ICチップが入っているVISAなどのクレジットカードのタッチで全ての地下鉄に乗れる。日本はSuicaで乗れるが、シンガポールでは外国人が行ってもすぐに乗れる。それでタクシーを使わなくて済んでしまう。逆に車を持っている人は少ない。車を輸入させない政策をとっていて車が非常に高い。それで街中も交通渋滞がなく、快適に過ごせる国でした。
街も安心。女性が夜10時過ぎに一人で歩いて帰れるくらいになっている。
振り返って日本を見ると、それだけの差が付いたというのにはかなりがっかりさせられました。
いつの間にか滞在費が安い都市に
国内では、今年のゴールデンウィークを見ると、自宅で過ごした人が46.8%でした。物価高、円安が原因で、GWに使う予算も3万円弱と昨年より1万円近く減少していた。
テレビなどでも、混み過ぎてスマホの電波が入らない、満員で江ノ電から景色が見えない、など「出かけなくて良かった」といった印象を与えるような話題が多く、外出を控えるムードができていた。
オーバーツーリズムも強調されGW中は外に出なくなった。スーパーとしては、夕方から客数が増えるなど変化があった。
英国・ホリデーマネーレポートで、滞在費のランキングを見ると1位がベトナム・ホイアン、2位南アフリカ・ケープタウン、3位ケニア・モンサバ、5位ポルトガル・アルカルヴェで、東京は世界4位で、滞在費が安い都市になった。
それがインバウンドが増えている理由で、日本滞在中の1人当たりの消費額を増やす工夫が必要。
暑い夏に備えた売場作りを!
今年6月以降を見ても定額減税が言われているが、あまり効果がないだろう。電気代の補助は終了し、円安による物価上昇、小売業の再編は続くでしょうし、企業間の優勝劣敗が明確化してくる。
こうした中、セルコとしても会員企業様と一緒になってどうするか、考えて実行していかないと大変になる時代と認識している。
当面の対策としては、まずは暑い夏に備えた売場作り。涼感のある食品、スタミナ食品もいつもより早く並べないといけない。ドラッグなども含めて暑さ対策グッズをどう売って行くか。小さな扇風機を1〜2台持たれているので、スーパーでも1〜2台買ってもらえればありがたいから是非スーパーで売って欲しい。あるいは寝苦しい夜の睡眠対策商品。体を冷やすモノとか、こうした季節商品をうまく売っていかないといけないと思う。
猛暑の中、来店してくださるお客様を涼しげな服装で迎えるとか、冷やして使えるマスクなどもアイデアとして考える。
これから皆で頑張って、2024年を乗り切っていきたいと思いますので宜しくお願いします。
皆さんご存じかと思いますが、ユニクロが5月23日に全国紙に“失われた30年と、失われなかった40年。”をキャッチフレーズにした全面広告を出しました。
確かに私たちは失われた30年と言っていますが、ユニクロにしたら、失われなかった40年なのです。平富郎エコス名誉会長が景気は自分で作るものと言われていますが、ユニクロはまさにそれを実行した好例です。
今から40年前に遡ると、ユニクロは1984年6月2日に広島市袋町の裏通りで1号店をオープンしました。開店時間は早朝6時という奇策。誰も来てくれないのでは?店長でさえそう思うほどでした。ところが大行列、というより大群衆が集まってきた。
「早朝から並んでくださったお客様になにか感謝をお伝えしたい!とお配りしたのが、あんぱんと牛乳でした。あの日の気持ちはユニクロの初心。いまへとつづく感謝祭の原点です。」と広告には書いてあります。
素晴らしいユニクロの成長と軌跡が1枚の広告で謳いあげられている。エコスさんはこれに近いことをやり、ここまでこられていると思いますが、私たちもこれに元気づけられると共に、かくありたいと思うところであります。
ユニクロの40年を顧みると、世界で3,500店、時価総額は12.7兆円、売上は3兆円超。海外事業が国内の1.5倍。アメリカ、ヨーロッパなど地域に合わせて経営判断できる体制を構築して更なる発展に向けてチャレンジしていこうとしています。
我々もこうした企業を模範にしながらやっていかないといけないと感じています。
「世界一」と言い始めた時から衰退始まる
一方で、成功していない企業もあります。
シャープの液晶は日本でしかできない、世界最先端のモノ作りを実現した、「世界の亀山モデル」と自画自賛していました。亀山工場は液晶パネルからテレビまでを一貫生産する、垂直統合型工場と言われていました。要するに部品から完成品まで造り上げた。2002年上期、シャープは米国のシェアで33.5%を占めた。メーカーが「我が社は世界一」と言い始めた時から衰退が始まっていて、2024年9月には大型液晶パネルの生産を終了します。
経営が苦しくなると、液晶パネルを海外メーカーに外販したり、コスト競争に巻き込まれ、2015年には台湾のホンハイの傘下に入り、2018年には黒字転換、2020年には大幅黒字で再建が完了した。22年には夢をもう一度と、堺ディスプレイ・プロダクト(SDP)を買い戻した。しかし2023年にはSDPの業績悪化で減損損失を計上。24年9月に大型液晶パネルの生産を終了することになったのです。
この例から、過去の栄光、成功体験に固執し冷静な状況判断が出来ず、結果として変化に背を向けたと言えます。平名誉会長が良く言われることですが、「成功の原因が失敗を作る」と感じています。
日本もシャープと同じで、失われた30年で国力は衰退。一人当たりのGDPは韓国、台湾に抜かれている。その中で、アニメの評価、インバウンド、外国人労働者で持ちこたえている状況。なんとなく昭和の成功体験の中で、世界の急激な変化に対応出来ないでいる。「日本がスゴイ」、という成功体験から、「日本がヤバイ」と変わっているのが現状。私たちもそれを日々感じながら経営しているのが現実だと思います。
成長著しいシンガポール
先日シンガポールに行ってきましたが、その発展を目の当たりにしてきました。
シンガポールの人口は日本の4%、面積は0.2%、GDPは6.3%。しかし一人当たりGDPは日本の約2倍。サービス産業、製造業を基盤に、情報、金融産業が急成長している。いろいろな意味でアジアのハブとしてトップに立っている。エアポートがハブになり、海運でもハブになっている。政治的にも安定していて、汚職も少なく、公的機関の透明性は高い。
1965年にマレーシアから独立し、中国人のリー・クワンユーが長く政治のリーダーでいて、その息子のリー・シェンロンにその座を譲り、シェンロンが今年の5月に任期を終えた事に伴いローレンス・ウォンが首相になったばかり。
成長の象徴になったマリーナベイ・サンズは2011年に開業している。3棟の屋上を船の形をした構造物で繋いでいる有名なホテルですが、現在までも統合型リゾートホテルとしてどんどん成長してきている。その中のショッピングセンターには世界のブランドが全て集中していて驚かされます。あれだけ集中しているのはおそらくあそこだけ。
シンガポール大学は世界のトップで東京大学よりかなり上に位置づけられています。
シンガポールの地下鉄に乗って驚きましたが、非常に乗り易い。東京の地下鉄の路線図ダイヤグラムが見やすいと他の国々のモデルになったことがあるが、シンガポールのダイヤグラムは非常に見やすい。一つのカードで乗り回れる。ICチップが入っているVISAなどのクレジットカードのタッチで全ての地下鉄に乗れる。日本はSuicaで乗れるが、シンガポールでは外国人が行ってもすぐに乗れる。それでタクシーを使わなくて済んでしまう。逆に車を持っている人は少ない。車を輸入させない政策をとっていて車が非常に高い。それで街中も交通渋滞がなく、快適に過ごせる国でした。
街も安心。女性が夜10時過ぎに一人で歩いて帰れるくらいになっている。
振り返って日本を見ると、それだけの差が付いたというのにはかなりがっかりさせられました。
いつの間にか滞在費が安い都市に
国内では、今年のゴールデンウィークを見ると、自宅で過ごした人が46.8%でした。物価高、円安が原因で、GWに使う予算も3万円弱と昨年より1万円近く減少していた。
テレビなどでも、混み過ぎてスマホの電波が入らない、満員で江ノ電から景色が見えない、など「出かけなくて良かった」といった印象を与えるような話題が多く、外出を控えるムードができていた。
オーバーツーリズムも強調されGW中は外に出なくなった。スーパーとしては、夕方から客数が増えるなど変化があった。
英国・ホリデーマネーレポートで、滞在費のランキングを見ると1位がベトナム・ホイアン、2位南アフリカ・ケープタウン、3位ケニア・モンサバ、5位ポルトガル・アルカルヴェで、東京は世界4位で、滞在費が安い都市になった。
それがインバウンドが増えている理由で、日本滞在中の1人当たりの消費額を増やす工夫が必要。
暑い夏に備えた売場作りを!
今年6月以降を見ても定額減税が言われているが、あまり効果がないだろう。電気代の補助は終了し、円安による物価上昇、小売業の再編は続くでしょうし、企業間の優勝劣敗が明確化してくる。
こうした中、セルコとしても会員企業様と一緒になってどうするか、考えて実行していかないと大変になる時代と認識している。
当面の対策としては、まずは暑い夏に備えた売場作り。涼感のある食品、スタミナ食品もいつもより早く並べないといけない。ドラッグなども含めて暑さ対策グッズをどう売って行くか。小さな扇風機を1〜2台持たれているので、スーパーでも1〜2台買ってもらえればありがたいから是非スーパーで売って欲しい。あるいは寝苦しい夜の睡眠対策商品。体を冷やすモノとか、こうした季節商品をうまく売っていかないといけないと思う。
猛暑の中、来店してくださるお客様を涼しげな服装で迎えるとか、冷やして使えるマスクなどもアイデアとして考える。
これから皆で頑張って、2024年を乗り切っていきたいと思いますので宜しくお願いします。